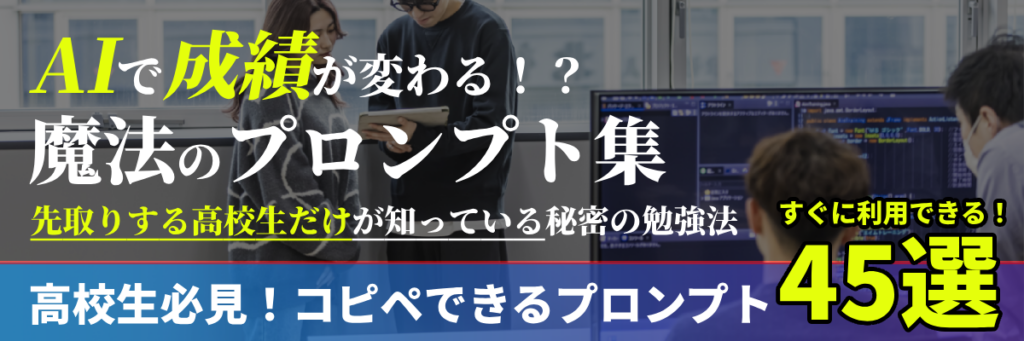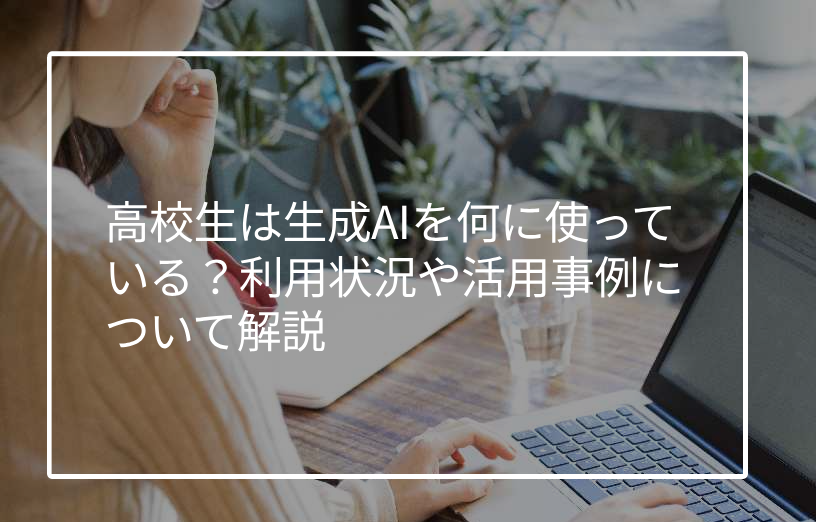
INDEX
生成AI(ジェネレーティブAI)は、蓄積した学習データを基に、オリジナルのコンテンツを生成できる人工知能です。「AIネイティブ世代」と呼ばれることもある現代の高校生は、生成AIを日々の学習や趣味などへ上手に取り入れています。
しかし、生成AIは決して完璧ではなく、さまざまな課題も含んでいます。生成AIの利用が、個人情報の漏えいや権利の侵害といった、重大な問題につながる可能性も否定できません。
本記事では、高校生の生成AI利用状況や活用事例、仕事への影響などを解説します。AIと共存する未来のために、ぜひお読みください。
高校生の生成AI利用状況
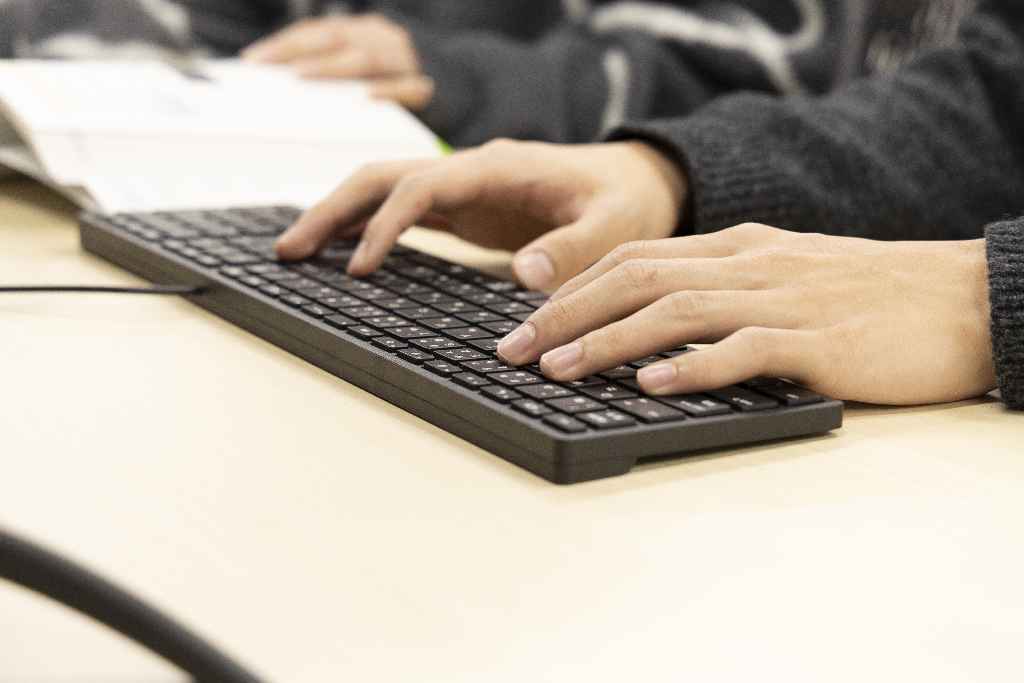
仙台大学が高校生2,184人を対象に行った調査によると、2024年3月時点で、生成AIを利用している生徒の割合は30.3%(約660人)でした。
生成AIを利用している高校生約600人に利用頻度を聞いたところ、最も多かった回答は「週に1回未満」であり、65.9%(約400人)に上りました。次に多かったのは「週に1回」の9.9%(約60人)です(※)。
※参考:仙台大学「学生と教員に対する生成AIの教育利用状況と意識に関する調査」p7,9.https://www.nii.ac.jp/event/upload/20241106-3_saito.pdf (参照2025-03-12)
高校生は生成AIを学習にどう使っているか

生成AIを利用している高校生は、日々の学習に取り入れているケースが多いです。企業や各地の学校でも、学生向けの生成AI講座を開催することが増えてきました。
高校生の学習における生成AIの具体的な活用事例には、以下のようなものがあります。
| 質問と解説 | 問題の解き方、苦手分野の学習方法を質問
教科書の補足説明、外国語の和訳、過去問題の解説 書籍など長文の要約 |
| 添削 | 問題の回答、レポート・小論文の添削 |
| 解説 | 教科書の補足説明、外国語の和訳、暗記内容の整理 |
| 入試対策 | 入試傾向の分析
問題の作成、過去問題の解説 |
高校生は生成AIを学習以外にも使っている

高校生の中には、生成AIを学習以外にも幅広く活用している生徒もいます。会話形式で気軽に扱える生成AIは、上手に活用できれば頼もしい存在です。
ここでは、学習以外での生成AI活用例を紹介します。
クリエイティブな活動
生成AIは文章や動画、画像作成などのクリエイティブな活動にも役立ちます。高校生向けのAI講座でも、創作系の技術を教えるケースがあるようです。
生成AIをクリエイティブな活動に役立てている事例には、以下のようなものがあります。
- 読書感想文や自由研究レポートの作成
- 作文やレポートのアイデア出し
- 小説やシナリオのアイデア出しと執筆
- SNSに投稿するコンテンツの作成
- 部活動のトレーニングメニューの作成
- 修学旅行のプラン作成
- ディベートの想定質問の作成
- ブレインストーミングのアイデア出し
生成AIの創作性を活用した事例
膨大な学習データを組み合わせて、オリジナルの回答を出せる生成AIは、幅広い用途での活用が可能です。高校生はその機能も上手に活用しています。
- 志望校選択のヒントを質問
- 大学受験における志望動機の作成
- 暇つぶしの会話
- プレゼント選び
- 調べ物
高校生が生成AIを使う際の注意点

生成AIには、注意しなければならないポイントが存在します。
ここでは、高校生が生成AIを使う際に気を付けるべき注意点を、3つピックアップして解説します。
- ハルシネーションに注意する
- プライバシーをオプトアウトで守る
- 著作権など権利に配慮する
ハルシネーションに注意する
生成AIには「ハルシネーション」と呼ばれる問題があります。これは生成AIが誤った情報を、さも正しいかのように出力してしまう現象です。ハルシネーションの語源は幻覚を意味し、生成AIが幻覚を見ているように事実とは異なる回答を出力する様子から、このような呼び名が付けられたとされています。
ハルシネーションには4つのタイプがあります。
| タイプ | 現象 | 原因 |
| 事実ハルシネーション | 架空の情報を事実として出力する | 生成AIが学習データの関連付けを誤る |
| 創造的ハルシネーション | 実際には存在しない理論や用語などの誤情報を作り出す | 生成AIが事実を無視して創造的に考えてしまう |
| 文脈ハルシネーション | 質問に対して関連性のない回答をする | 生成AIがプロンプト(生成AIに与える命令文や質問文などの指示)を正しく解釈できない |
| 構造ハルシネーション | 期待と異なる回答の仕方をする | 適切ではない回答形式を認識してしまう |
※本分類は一般的理解のための整理であり、学術的分類基準は研究により異なります。
生成AIが出力したテキストなどのコンテンツは、人間の徹底したファクトチェック(正しいかどうかの確認)が不可欠です。内容の真偽はもちろん、情報の鮮度や質問との整合性もチェックしましょう。
プライバシーをオプトアウトで守る
生成AIにおけるオプトアウトとは、入力した情報を学習に使われないようにすることです。
オプトアウトをしていない場合、生成AIは「ユーザーが生成AIとのやり取りで入力した情報」を、学習データとして蓄積してしまいます。
つまり、生成AIに入力した個人情報や秘密の情報は、学習データに取り込まれる恐れがあります。その情報が他のユーザーへの回答として表示されれば、個人情報や秘密が漏えいしてしまうでしょう。
「ChatGPT」や「Google Gemini」では、チャット履歴をオフにするとオプトアウトができます。以下はその方法です。
| ChatGPT | 画面左下のユーザーアイコンをクリック 「Settings(設定)」を開く「Data Controls(データ管理)」を開く「Chat history & training(チャット履歴とトレーニング)」をオフにする |
| Google Gemini | 左下の「アクティビティ」アイコンをクリック
「Geminiアプリ アクティビティ」をオフにする |
※UIは変更される場合があります。最新の設定方法は公式サポートページをご確認ください。
チャット履歴をオフにすると、会話履歴の参照ができなくなります。また、ユーザーの入力データを学習しないため、回答の精度が上がらなくなる可能性もあります。
著作権など権利に配慮する
生成AIを使って作成したコンテンツが、既存の著作物と類似している場合「著作権侵害」となる可能性があります。
文化庁では、生成AIの著作物の利用について、人がAIを利用せずに作成した場合と同様に判断すると定めています。
文化庁が定める著作権侵害の要件は、以下の通りです。表の1、2のどちらか(あるいは両方)に当てはまれば、著作権侵害になります。
| 1.類似性
(他人の著作物と同じ、または似ている) |
他人の著作物の「表現上の本質的な特徴」を感じられるか(単なる事実の記載やありふれた表現、作風や画風は含まれない) |
| 2.依拠性
(他人の著作物を参考に作成している) |
見たり聞いたりした他人の著作物を参考にしたり、似せたりしているか(意図せず偶然に一致した場合(独自創作など)を除く) |
※著作権侵害の判断は複雑で、個別事案により異なります。詳細は文化庁ガイドラインや専門家にご相談ください。
生成AIで作成したコンテンツが他人の著作物と類似性がある作品は、SNSなどで公表する前に、著作権者の許諾を得る必要があります。類似性がなくなるよう大幅に手を加えるのも方法の一つです。
高校生が将来的に生成AIの知識を生かせる仕事

近年、生成AIはビジネスシーンでも多く使われるようになりました。学生時代に生成AIの知識を身につけておくと、将来の職業選択の際、さまざまな仕事に応用できる可能性が出てきます。
ここでは、高校生が生成AIの知識を生かせる仕事の一例を紹介します。
生成AIの知識を生かせる職種
生成AIに関わる求人状況は「ソフトウェア開発」に関連する職種の割合が多いようです。具体的には以下の職種です。
- Webエンジニア
- システムエンジニア
- フロントエンドエンジニア
ソフトウェア開発以外では、次の職種の求人割合も上位に入っています。こちらは、生成AIの利用によって品質の向上、業務工数削減などができる職種です。
- Webデザイナー
- UI/UXデザイナー
- 事務、営業
生成AIに関わる新しい仕事
生成AIの普及によって新しく誕生した仕事や、これから生まれると予測されている仕事もあります。
特に需要が急増しているといわれるのが「プロンプトエンジニア」です。プロンプトエンジニアとは、生成AIに入力するプロンプトを作る専門家を意味します。精度の高い回答を引き出せるプロンプトの作成はもちろん、AIモデルの分析やプロンプトの最適化も行います。
以下はAI(生成AI含む)によって新しく生まれた、あるいは生まれると予測されている仕事の一例です。
| 職種 | 業務内容 |
| データ探偵 | ● IoT機器やニューラルネットワークが収集したデータの分類と分析をする
● 分析結果に基づく顧客へのコンサルティングをする |
| ゲノム・ポートフォリオ・ディレクター | ● 新薬を一般消費者に販売するための戦略を立てる (AIを用いた遺伝子研究を新しい治療に活用している) |
| サイバーシティアナリスト | ● 都市に配置したセンサーの収集データをセキュリティ管理する
● 故障したセンサーを修理する |
| エッジコンピューティング専門家 | ● 端末利用者の周囲にサーバーを分散させて応答速度を上げる
● 端末の故障などのトラブルをいち早く把握する |
高校生の未来が変わる?

生成AIが人間の未来にどのような変化をもたらすかは、専門家の間でも意見が分かれており、正確な予想はされていません。これからの時代を生きる高校生が、生成AIとどのように共存していくことになるのかは、未知数と言えるでしょう。
2000年代に始まった第3次AIブームでは、AIの囲碁プログラムが世界トップレベルのプロ棋士に勝利し、人々を驚かせました。第4次AIブームと呼ばれている現代では、AIが人間の知能と同じレベルに達する「シンギュラリティ」が起こる可能性も指摘されています。
ここでは、高校生の未来に起こり得ることについて解説します。
高校生の職業選択とAI
AI(生成AIを含む)が登場して以来、AIが人間の仕事を奪う可能性について世界的に取り上げられてきました。「野村総合研究所とオックスフォード大学の共同研究(2015年)によると、日本の労働者の49%が従事する業務は、10~20年後にAIやロボットで代替可能と推計されています。
AIの発展と普及により、多くの仕事が人間から機械にシフトされる可能性があります。自動化が進んでいる製造業、チャットボットで応答できるカスタマーサービス、単純作業やデータ処理などはその一例です。
一方で創造性や判断力、抽象的な概念などが必要な職業は、AIに仕事を奪われにくいとされています。人と人とのコミュニケーションが不可欠な職業も同様です。例として営業職や介護士、アートディレクター、教員などの職業が挙げられます。
「AIに仕事を奪われる」という予測を大きく危惧する方も多いかもしれませんが、先のことを正確に予測することは困難です。高校生のうちから「どのような道に進みたいのか、どうありたいか」と未来予想図を描き、AIにはできないスキルや知識を習得したり、AIをうまく扱うスキルを習得したりしていくことが大切です。
※出典:野村総合研究所「日本の労働人口の49%が人工知能やロボット等で代替可能に」
高校生の未来とシンギュラリティ
前述の通り、シンギュラリティ(技術的特異点)とは「AIが人間の知能を超越し、それ以降の技術進歩が予測不可能になる転換点」です。それほど新しい言葉ではなく、AI研究家の間では1980年代から使われてきました。
シンギュラリティの提唱者は、到達時期を2045年と予想しています。その予想が正しければ、現在の高校生が社会の第一線で活躍している時期に、世界の労働事情が一変する可能性も否定できません。
しかし「AIは人間のために作られており、独自の目標や欲求を持っているわけではないため、人間と同一視して語ることはできない」とする専門家もいます。
AIが将来の世界をどのように変化させるかを正確に予測するのは困難なため、学生のうちに専門性の高い分野を学び、知識とスキルを身につけておくことが大切です。
高校生は生成AIと共存する将来を考えよう
生成AIを含めたAIがどのように発展し、社会にどこまで影響を与えるのかは、未知数です。しかし、AIは現在進行形で進化を続けています。現代の高校生は、生成AIとの共存を前提に将来を考える必要があるのでしょう。
生成AIに関連する仕事の中で、特に需要が多い分野はソフトウェア開発です。システムに関する知識はこれからの時代を生きるための強力なスキルになるでしょう。
生成AIと共存する社会に備え、システム開発のスキルを学びたいなら

仙台工科専門学校では2025年情報システム学科/高度情報システム学科を新設し、2年制の情報システム学科は、システム開発の中心となるIT技術者の育成を目的としています。3年制の高度情報システム学科は、システム設計や開発が行える総合的なITエンジニアを養成するさらに専門的なコースです。
生成AIと共存する社会に備え、システム開発のスキルを学びたいと考えている高校生の方には特におすすめです。
この学科では、初心者からAIやITをしっかり学んで、プロになるカリキュラムを用意しています。ITスキルの習得やAIシステムについての知識や開発技術だけでなく、適切なプロンプトを設計するための論理的思考力を養う授業も行うため、AIの開発、活用技術を身につけたAIを制する人材をめざせます。
情報システム学科/高度情報システム学科のオープンキャンパスでは下記テーマで体験授業も実施しています。
ChatGPT(生成AI)を使って未来のプログラミングを体験しよう!
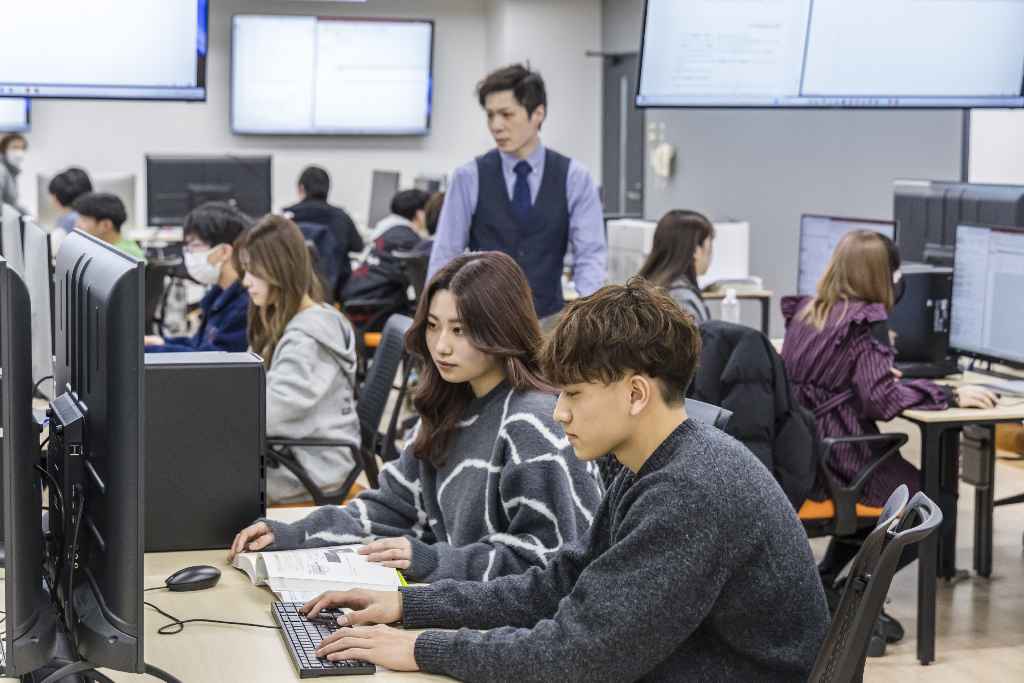
今話題のAIスキルも身につく!プロンプト(AIへの指示文)をうまく使って効率的にプログラミングしてみよう。0からのスタートでどんな業種にも生かせるAI人材をめざそう!さらにオープンキャンパスではさらに特別なプロンプトも配布します。
▲上記コラムもおすすめ。
まずは、オープンキャンパスで疑問や不安を解決しよう!

仙台駅から徒歩7分。情報・建築・インテリア・大工・測量・土木が学べる専門学校です。
「建築・大工・測量・土木・情報」の7学科を設け、充実した環境の下で行われる現場さながらの実習で即戦力となる技術を習得。きめ細かい試験対策で国家資格取得を目指し、業界の最前線で活躍する人材を育成します。